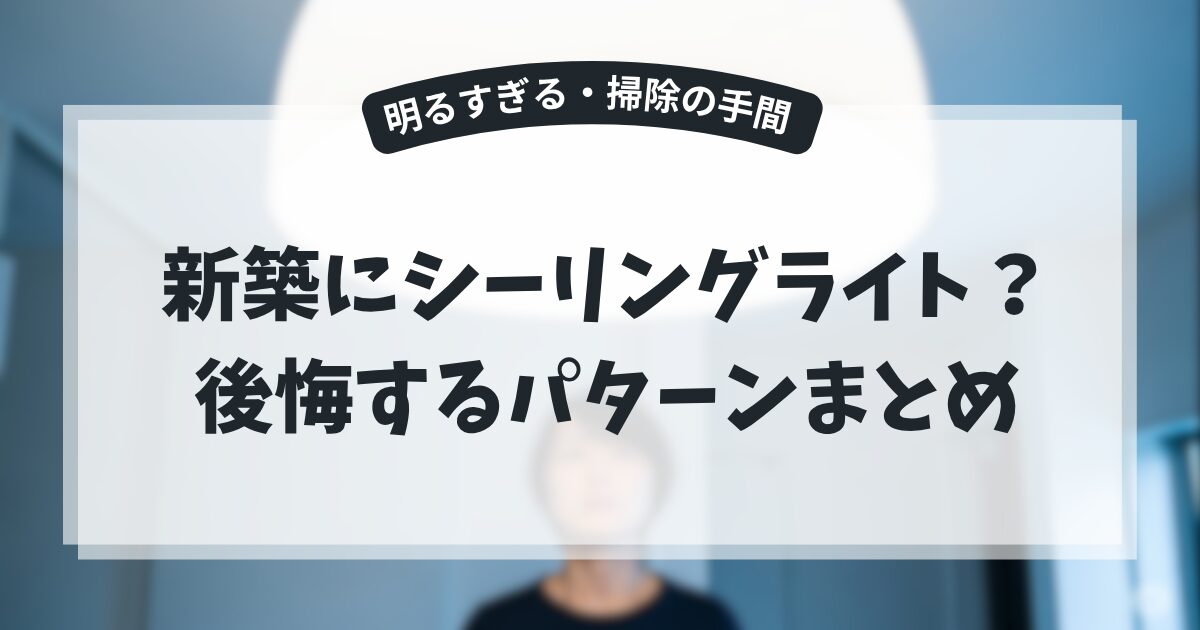新築の家づくりにおいて、照明計画は部屋の印象を大きく左右する重要な要素です。中でもシーリングライトは手軽で人気ですが、「新築でシーリングライトを選んで後悔した」という声は少なくありません。
シーリングライトのみの照明計画では、おしゃれな空間を演出しきれなかったり、想定外に費用がかさんだりといった、よくある失敗談がいくつも存在します。
また、LEDシーリングライトは10年持たないという話や、それぞれの照明が持つメリット、デメリットを十分に理解しないまま進めてしまうことも後悔の原因です。特に、家の中心となるリビングでは、ダウンライトとシーリングどっちが良いのか、あるいはリビングでダウンライトとシーリングの併用は可能なのか、という疑問は尽きません。
一方で、ダウンライトを設置したものの結局使わない、ダウンライトをやめたいと感じるケースも。この記事では、そんな新築の照明選びに関するあらゆるお悩みを解決するため、後悔しないための具体的なポイントを徹底解説します。
新築でシーリングライトを選ぶ際の後悔パターン

新築照明でよくある失敗談とは?
新築時の照明計画では、夢や理想が膨らむ一方で、具体的な生活をイメージしきれずに失敗してしまうケースが後を絶ちません。多くの人が直面する後悔ポイントを知ることで、同じ過ちを避けることができます。
代表的な失敗談は「部屋の明るさが適切でなかった」というものです。例えば、「リビングをダウンライトだけにしたら、ソファ周りが思ったより暗く、読書や作業がしづらい」「逆に寝室が明るすぎてリラックスできない」といった声が聞かれます。これは、照明の数や種類、ワット数(明るさ)、そして光の広がり方(拡散・集光タイプ)の選定ミスが主な原因です。
また、「天井がゴチャゴチャして見える」というのも、よくある後悔のひとつ。特にダウンライトは、スッキリした空間を目指して採用したにもかかわらず、数を増やしすぎた結果、天井に穴がたくさん開いているような雑然とした印象を与えてしまうことがあります。
配置計画の失敗にも注意
家具や家電の配置を考慮せずに照明を設置した結果、「テレビ画面に照明が映り込んで見づらい」「ダイニングテーブルの位置をずらせなくなった」という失敗も起こりがちです。照明計画は、家具のレイアウトとセットで考えることが鉄則と言えるでしょう。
さらに、掃除の手間を見落として後悔するケースもあります。シーリングライトのカバー内に虫の死骸が溜まってしまったり、吹き抜けのような高い位置に設置したスポットライトやブラケットライトのホコリ掃除が大変だったり、といった点は、設計段階ではなかなか気づきにくいポイントです。
設置するメリット・デメリット

シーリングライトは、日本の住宅で最もポピュラーな照明器具であり、多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。両方を理解することが、後悔しない照明選びの第一歩です。
最大のメリットは、1台で部屋全体を均一に明るく照らせる点にあります。特にリビングや子ども部屋など、活動のメインとなる空間では十分な明るさを確保しやすく、実用性に優れています。また、取り付けが比較的簡単で、製品価格も手頃なものが多いため、初期費用を抑えたい場合には有力な選択肢となります。
しかし、その「均一な明るさ」がデメリットになることも。光に強弱がないため、部屋全体がのっぺりとした印象になり、おしゃれなカフェのような陰影のある空間を作るのには不向きです。天井に大きな器具が設置されるため、天井の高さや部屋の広さによっては圧迫感を与えてしまう可能性もあります。
| メリット | ✅ 1台で部屋全体を明るくできる ✅ 取り付けや交換が比較的簡単 ✅ 製品価格が手頃なものが多い ✅ 調光・調色機能付きの製品が豊富 |
|---|---|
| デメリット | ✅ 器具の存在感による圧迫感 ✅ 陰影がなく、のっぺりした印象になりがち ✅ 製品によってはカバー内に虫が入りやすい ✅ スタイリッシュな空間演出しにくい |
最近は薄型でおしゃれなデザインのシーリングライトも増えています。ただし、ダウンライトや間接照明のように「光で空間をデザインする」という自由度は低いため、インテリアに強いこだわりがある場合は、他の照明との組み合わせを検討するのがおすすめです。
LEDシーリングライトは10年持たない?

「LEDの寿命は長いと聞いていたのに、シーリングライトは10年で交換が必要って本当?」という疑問を持つ方は少なくありません。この話には少し解説が必要です。結論から言うと、「LEDシーリングライトが10年持たない」というのは、LED光源そのものではなく、照明器具本体の寿命を指しています。
確かに、LEDチップ自体の寿命は非常に長く、一般的に約40,000時間とされています。これは1日に10時間点灯したとしても、10年以上にわたって使用できる計算です。しかし、シーリングライトはLEDチップ以外にも、プラスチック製のカバーや、内部の電子部品、電源部分など、多くのパーツで構成されています。
これらの部品は、使用環境や時間経過とともに熱や湿気で劣化していきます。カバーが変色したり、ひび割れが起きたり、内部の回路が故障して点灯しなくなったりすることがあるのです。このため、一般社団法人日本照明工業会では、照明器具の交換時期の目安を8~10年としています。(参照:日本照明工業会)
照明器具の劣化サイン
以下のような症状が見られたら、たとえ点灯していても交換を検討するサインです。
- カバーに黄ばみやヒビがある
- 点灯・消灯時に異音がする
- 点灯が不安定になったり、ちらついたりする
- 焦げくさい臭いがする
安全のためにも、設置から10年近く経過した照明器具は、一度点検してみることをおすすめします。
おしゃれな空間にならない圧迫感の原因

シーリングライトを設置したら、「なんだか部屋が狭く見える」「おしゃれなイメージと違う」と感じてしまうことがあります。その主な原因は、天井の高さと照明器具の大きさ(特に厚み)のバランスが取れていないことにあります。
日本の一般的な住宅の天井高は、240cm前後で設計されることが多いです。この空間に厚みのあるシーリングライトを取り付けると、天井が実際よりも低く感じられ、圧迫感につながってしまいます。特に、身長の高い方にとっては、頭上の照明がより近くに感じられるため、窮屈な印象を受けやすくなります。
圧迫感を避けるためのひとつの目安として、「自分の身長から照明器具の下面までの距離を50cm以上確保する」という考え方があります。例えば、天井高が240cmの部屋に住む身長170cmの人であれば、照明器具の高さ(厚み)は20cm以下のものを選ぶと、圧迫感なく快適に過ごせると言われています。(240cm - 170cm - 50cm = 20cm)
薄型デザインを選んでスッキリ見せる
近年、シーリングライトは技術の進歩により、非常に薄型のデザインが増えています。厚みが10cmを切るようなスリムなモデルを選べば、器具の存在感が薄れ、天井がフラットに見えるため、部屋全体をスッキリと広く見せることが可能です。デザイン性を重視する場合は、照明器具の厚みに注目して選ぶようにしましょう。
照明計画で考えるべき費用の問題
新築の照明計画において、デザインや機能性と同じくらい重要なのが費用です。特に、おしゃれな空間を演出しやすいダウンライトをメインに考えると、シーリングライトで計画するよりも費用が高くなる傾向があるため注意が必要です。
理由は、ダウンライトが1台で照らせる範囲がシーリングライトに比べて狭いことにあります。部屋全体に十分な明るさを確保するためには、多くの台数を設置する必要があり、その分、器具代と電気工事の設置費用がかさんでしまうのです。
ここで、具体的な比較例を見てみましょう。インプットした情報によると、ある住宅の20.25畳のリビングを異なる照明で計画した場合、費用には大きな差が出ています。
| 照明の種類 | 必要個数 | 価格(設置費含む) |
|---|---|---|
| ダウンライト | 16個 | 132,800円 |
| シーリングライト | 3個 | 64,550円 |
上記はあくまで一例ですが、ダウンライトをメインにすると倍以上の費用がかかる可能性があることが分かります。予算をオーバーしないためには、どこにコストをかけるかメリハリをつけることが重要です。
コストを抑える有効な方法は、部屋の用途によって照明を使い分けることです。例えば、家族が集まるLDKや来客を迎える玄関はデザイン性を重視してダウンライトや間接照明を取り入れ、寝室や子ども部屋などプライベートな空間は、コストパフォーマンスに優れたシーリングライトを選ぶ、といった「適材適所」の考え方が賢い選択と言えるでしょう。
新築のシーリングライトによる後悔を避ける照明選び

シーリングライトのみで部屋は暗い?

「シーリングライト1台だけだと、部屋が暗く感じそうで不安」という声をよく聞きます。結論から言うと、部屋の広さに適した光量(ルーメン)のシーリングライトを選べば、生活に必要な明るさを確保することは十分に可能です。しかし、「明るい」ことと「心地よい光の空間」であることは、必ずしもイコールではありません。
シーリングライトのみの照明計画で起こりがちなのが、「部屋の中心は明るいが、壁際や天井が暗く見える」という現象です。シーリングライトは真下と横方向に光を放ちますが、天井そのものを照らす光は弱いため、どうしても天井面に影ができてしまいます。壁面まで光が届きにくいと、部屋の隅が暗い印象になり、空間全体が狭く感じられてしまうことがあります。
間接照明で光のムラを解消
この問題を解決するには、シーリングライトに加えて間接照明をプラスするのが効果的です。例えば、壁を照らすブラケットライトや、天井に向けて光を放つフロアスタンドなどを置くことで、部屋の隅々まで光が回り、空間に奥行きと広がりが生まれます。シーリングライトを消して間接照明だけにすれば、リラックスした落ち着きのある雰囲気も演出でき、生活シーンに合わせた光の使い分けが可能になります。
リビングはダウンライトとどっちがいい?
リビングのメイン照明として、ダウンライトとシーリングライトのどちらを選ぶべきか。これは新築の照明計画における永遠のテーマとも言える問題です。正解はなく、どのような空間にしたいか、どんな暮らし方をしたいかによって最適な選択は異なります。
それぞれの照明の特徴を比較してみましょう。
| 比較項目 | ダウンライト | シーリングライト |
|---|---|---|
| デザイン性 | ◎ 天井がフラットになりスッキリした印象。モダンでおしゃれ。 | △ 器具の存在感があり、圧迫感を感じることも。 |
| 明るさの質 | △ 複数の光で照らすため、明るさにムラが出やすい。 | ◎ 1台で部屋全体を均一に明るく照らせる。 |
| 空間演出 | ◎ 陰影を作りやすく、メリハリのある立体的な空間を演出できる。 | △ 光が均一なため、のっぺりした印象になりやすい。 |
| 初期費用 | △ 複数台の設置が必要で、器具代・工事費ともに高くなりがち。 | ◎ 器具代が比較的安価で、工事も容易。 |
| メンテナンス | △ 一体型は器具ごとの交換となり、電気工事が必要。 | ◎ 器具の交換は自分で簡単にできる。 |
このように、スッキリとしたデザイン性や空間のおしゃれさを最優先するならダウンライト、実用性やコストパフォーマンス、メンテナンスのしやすさを重視するならシーリングライトに軍配が上がります。どちらか一方に決めるのではなく、次の項目で解説する「併用」という選択肢も視野に入れると、より満足度の高いリビングが実現できるでしょう。
リビングはダウンライトと併用が最適解
ダウンライトとシーリングライト、それぞれのメリット・デメリットを考えると、リビングの照明計画における最適解は「両方を併用する」ことにあると言えます。互いの長所で短所を補い合うことで、デザイン性と機能性を両立した、非常に快適で贅沢な空間を作り出すことが可能です。
併用の基本的な考え方は、生活のベースとなる全体の明るさをシーリングライトで確保し、ダウンライトを補助的な照明として使うというものです。これにより、以下のようなメリットが生まれます。
- 明るさの確保とコスト削減の両立
ダウンライトのみでリビング全体の明るさを確保しようとすると、かなりの数が必要になりコストもかさみます。しかし、メインにシーリングライトを置くことで、ダウンライトの数を最小限に抑えられ、費用を節約できます。天井がダウンライトだらけでゴチャゴチャする、という失敗も防げます。 - シーンに合わせた光の使い分け
家族で団らんする時や子どもが勉強する時は、シーリングライトとダウンライトを両方点灯してしっかり明るく。夜、映画を見たり音楽を聴いたりしてリラックスしたい時は、シーリングライトを消してダウンライトだけにする。このように、生活シーンに合わせて光の雰囲気を自由自在にコントロールできます。
例えば、リビングの中心にデザイン性の高いシーリングライトを1台設置し、テレビの上やソファ周り、壁際などに数個のダウンライトを配置するだけでも、空間の質は格段に向上します。併用は、まさに「いいとこ取り」の賢い照明計画なのです。
意外と多い?ダウンライトを使わない理由

おしゃれな空間を目指して間接照明やダウンライトを多めに設置したものの、「実際に住んでみたら、ほとんど使っていない」という後悔の声は意外なほど多く聞かれます。これは、「なぜ間接照明が必要なのか」という目的意識が曖昧なまま、雰囲気だけで設置してしまった場合に起こりがちな失敗です。
ダウンライトや間接照明が「宝の持ち腐れ」になってしまう主な理由は、以下の通りです。
- 他の照明で十分明るいから
メインとなるシーリングライトやリビングの基本照明だけで日常生活に支障がない場合、わざわざ補助的な照明を点けるという一手間を面倒に感じてしまい、次第に使わなくなります。 - 電気代が気になるから
特に近年の電気代高騰を受け、節電意識が高まっています。生活に必須ではない装飾的な照明は、真っ先に節電の対象となりがちです。「点けなくても困らないなら消しておこう」という心理が働き、結果的に点灯機会が失われます。
間接照明は「目的」を持って計画しよう
間接照明を有効活用するためには、「壁に飾った絵を照らしたい」「夜、手元だけを優しく照らして読書がしたい」といった具体的な使用目的を明確にすることが大切です。目的もなく「なんとなくおしゃれだから」という理由で設置すると、使わない照明にお金をかけただけ、という後悔につながる可能性があります。
ダウンライトをやめたいと感じる瞬間
ダウンライトは空間をスタイリッシュに見せてくれますが、その特性ゆえに「やめたい」「他の照明にしておけばよかった」と感じる瞬間もあります。主な原因は、「交換の手間」と「レイアウトの不自由さ」です。
最も大きな問題は、交換・メンテナンスの手間です。現在の主流であるLED一体型のダウンライトは、光源(LED)と器具が一体化しているため、寿命が来た際には照明器具ごと交換する必要があります。この作業には電気工事士の資格が必要なため、シーリングライトのように自分で手軽に交換することができず、専門業者に依頼する費用と手間がかかります。
一体型から他の照明への変更は困難
一度一体型ダウンライトを設置すると、そこからペンダントライトなどに変更するのは非常に困難です。天井の埋め込み穴を塞ぐ工事や、新たな配線工事が必要となり、大掛かりなリフォームになってしまうケースもあります。
また、ダウンライトは設置場所が固定されてしまうため、模様替えの自由度が低い点もデメリットです。例えば、ソファやダイニングテーブルの配置を変えたら、「照明の真下からズレて手元が暗くなった」「寝転がるとダウンライトの光が直接目に入って眩しい」といった問題が発生することがあります。将来的なライフスタイルの変化に対応しづらい点は、採用前に十分理解しておくべきでしょう。
新築のシーリングライトにまつわる後悔を防ぐ知識
新築の照明計画で後悔しないためには、シーリングライトやダウンライトなど、各照明の特性を深く理解し、自分のライフスタイルに合った選択をすることが重要です。最後に、この記事で解説した要点をまとめます。